バーンスタイン/マーラー交響曲第10番 [音楽]
昨日3月29日(金)をもって令和5年度の仕事は終わりました。
来週月曜は令和6年度の始まりの日,仕事に決別するまであとわずかになりました。
この1,2週間,これまでになかった忙しさでしたが,さすがに昨日はホッとして夜は抑えていたお酒を飲みました。
昔,中学校の音楽室にはバッハ,ベートーヴェン,モーツァルトなど偉大な作曲家の肖像が掲げられていましたが,現在盛んに聞かれている(私の好みの?)マーラーやブルックナーなどはありませんでした。何回かにわたり,マーラーの交響曲をバーンスタインの指揮でDVDで聞いてきましたが,今日は最後の交響曲第10番です。
この曲は,マーラーの最後の交響曲ですが未完です。
マーラーの遺稿では5楽章の予定のようでしたが,マーラーによって書かれたのは第1楽章「アダージョ」だけで,その他の楽章はマーラーの遺稿などを基に多数の人の補筆によって全曲完全版と言われるものが世に出ています。
国際マーラー協会はマーラーの手による第1楽章のみを「全集版」として出版しており,バーンスタインは,この第1楽章のみを演奏しています。
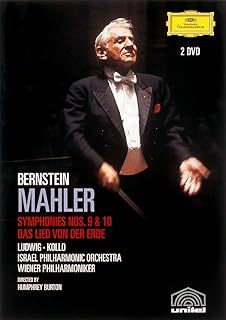
1974年10月 ウィーン コンツェルトハウス(ライブ) レナード・バーンスタイン指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
マーラーの第9番は,終楽章がアダージョで終わります。
10番は第1楽章がアダージョ,長大な9番のアダージョは,クライマックスは盛り上がりそして消え入るように終わるのですが,10番は,静かにビオラの合奏に始まります。
終始,緩やかに,9番のようなダイナミックな高揚はありません。
私には9番のアダージョに連続しているように感じられるのです。
現在,多数の補訂完成版の録音が流通していますが,バーンスタインがそれによらずアダージョのみを演奏したのは,マーラーは,この楽章によって「我々に別れを告げたのである。」と言っているのではないかという気がしてなりません。
マーラーは,1910年この曲の作曲にとりかかりましたが,翌1911年死去により10番は未完となったのです。
来週月曜は令和6年度の始まりの日,仕事に決別するまであとわずかになりました。
この1,2週間,これまでになかった忙しさでしたが,さすがに昨日はホッとして夜は抑えていたお酒を飲みました。
昔,中学校の音楽室にはバッハ,ベートーヴェン,モーツァルトなど偉大な作曲家の肖像が掲げられていましたが,現在盛んに聞かれている(私の好みの?)マーラーやブルックナーなどはありませんでした。何回かにわたり,マーラーの交響曲をバーンスタインの指揮でDVDで聞いてきましたが,今日は最後の交響曲第10番です。
この曲は,マーラーの最後の交響曲ですが未完です。
マーラーの遺稿では5楽章の予定のようでしたが,マーラーによって書かれたのは第1楽章「アダージョ」だけで,その他の楽章はマーラーの遺稿などを基に多数の人の補筆によって全曲完全版と言われるものが世に出ています。
国際マーラー協会はマーラーの手による第1楽章のみを「全集版」として出版しており,バーンスタインは,この第1楽章のみを演奏しています。
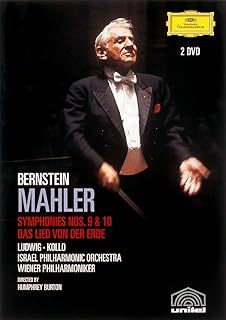
1974年10月 ウィーン コンツェルトハウス(ライブ) レナード・バーンスタイン指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
マーラーの第9番は,終楽章がアダージョで終わります。
10番は第1楽章がアダージョ,長大な9番のアダージョは,クライマックスは盛り上がりそして消え入るように終わるのですが,10番は,静かにビオラの合奏に始まります。
終始,緩やかに,9番のようなダイナミックな高揚はありません。
私には9番のアダージョに連続しているように感じられるのです。
現在,多数の補訂完成版の録音が流通していますが,バーンスタインがそれによらずアダージョのみを演奏したのは,マーラーは,この楽章によって「我々に別れを告げたのである。」と言っているのではないかという気がしてなりません。
マーラーは,1910年この曲の作曲にとりかかりましたが,翌1911年死去により10番は未完となったのです。
バーンスタイン/マーラー交響曲第9番 [音楽]
3月も終盤,仕事の方は尻に火がついたような状態です。
混乱しないように,十分な点検を欠かさず無事乗り越えたいと自戒しながら進めないといけません。
今日は土曜で休日,そのような時にこそ音楽を聞いて心穏やかに過ごしたいものです。
バーンスタイン指揮のマーラーをDVDで見て聞いてきましたが,今日は交響曲第9番です。
完結したマーラーの最後の交響曲です。
バーンスタインにとってマーラーの9番は,とても評価の高いものですが,更に,一期一会のベルリンフィルとの生涯一度だけの演奏もこの9番です。
今回は,ウィーンフィルハーモニー管弦楽団をカラヤンの牙城であるベルリンフィルハーモニーホールで指揮したものです。
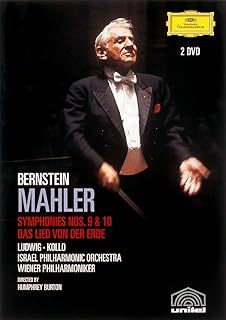 1971年3月 ベルリンフィルハーモニーホール レナード・バーンスタイン指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
1971年3月 ベルリンフィルハーモニーホール レナード・バーンスタイン指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
4楽章のこの曲は第1楽章と第4楽章が27分を超える長大なもので,最後の第4楽章をアダージョで締めくくります。ゆっくり第1楽章が始まりますが,最後のアダージョでクライマックスに至ります。
アダージョは,第5番の第4楽章「アダージェット」を思わせますが,ダイナミックに盛り上がり,そして消え入るように終わります。
マーラーは,「きわめて遅く,そして控えめに」と書いているようですが,バーンスタインの指揮はこの最終楽章で渾身の音楽を作ります。
マーラーには未完の交響曲第10番がありますが,マーラーの手になる楽章は,くしくも「アダージョ」です。次回はその交響曲第10番にします。
混乱しないように,十分な点検を欠かさず無事乗り越えたいと自戒しながら進めないといけません。
今日は土曜で休日,そのような時にこそ音楽を聞いて心穏やかに過ごしたいものです。
バーンスタイン指揮のマーラーをDVDで見て聞いてきましたが,今日は交響曲第9番です。
完結したマーラーの最後の交響曲です。
バーンスタインにとってマーラーの9番は,とても評価の高いものですが,更に,一期一会のベルリンフィルとの生涯一度だけの演奏もこの9番です。
今回は,ウィーンフィルハーモニー管弦楽団をカラヤンの牙城であるベルリンフィルハーモニーホールで指揮したものです。
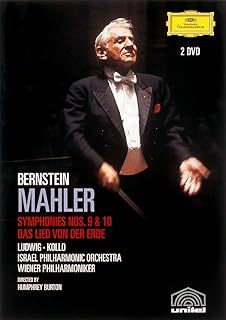 1971年3月 ベルリンフィルハーモニーホール レナード・バーンスタイン指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
1971年3月 ベルリンフィルハーモニーホール レナード・バーンスタイン指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団4楽章のこの曲は第1楽章と第4楽章が27分を超える長大なもので,最後の第4楽章をアダージョで締めくくります。ゆっくり第1楽章が始まりますが,最後のアダージョでクライマックスに至ります。
アダージョは,第5番の第4楽章「アダージェット」を思わせますが,ダイナミックに盛り上がり,そして消え入るように終わります。
マーラーは,「きわめて遅く,そして控えめに」と書いているようですが,バーンスタインの指揮はこの最終楽章で渾身の音楽を作ります。
マーラーには未完の交響曲第10番がありますが,マーラーの手になる楽章は,くしくも「アダージョ」です。次回はその交響曲第10番にします。
バーンスタイン/マーラー交響曲第8番「千人の交響曲」 [音楽]
3月も折り返し点,いよいよ令和5年度もあとわずか,確定申告も最後の日,やっと合同庁舎の駐車場が使えるようになりました。毎年のことで税務署の来庁者で駐車場が混雑し,ほとんど駐車場を利用できません。
レナード・バーンスタイン指揮のマーラー作曲交響曲をDVDで聞いてまいりましたが,今日は第8番にしました。
この曲は,後に言われるようになった「千人の交響曲」のとおり,巨大な演奏者群を要する大作です。
フルオーケストラのほか,パイプオルガン,男声,女声ノソリスト8人,今回は3つの合唱団(それぞれに合唱指揮者)等,この演奏会を聞くことができる人は幸せと言えるでしょう。
今回の演奏は,1975年8月のザルツブルグ音楽祭にこの曲が演奏されたのを機会にウィーンで演奏されたライブDVDです。
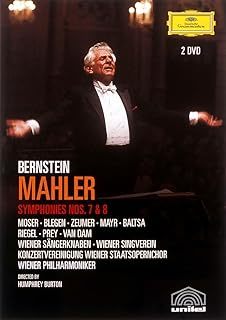
1975年8月,9月ウィーン,コンツェルトハウス レナード・バーンスタイン指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 5人の女声ソリスト,3人の男声ソリスト ウィーン国立歌劇場合唱団,ウィーン楽友協会合唱団,ウィーン少年合唱団
第1部と第2部に構成され,第1部はラテン語による聖歌,第2部はゲーテの「ファウスト」第2部の最後の部分をテキストにしているそうです。
この曲は,全曲,声楽と管弦楽,オルガンが一体となり奏でられる,いわば「合唱交響曲」です。
ベートーヴェン」の第9では第4楽章だけですし,マーラーの他の曲でも一部の楽章ですから,形の上でも一線を画している巨大な曲です。
第1部はパイプオルガンと合唱が聞く者を圧倒します。
第2部はソリスト,合唱がファウストからのテキストを歌い,オーケストラと最終章に至ります。
声楽ソリスト,合唱,オーケストラ渾身の演奏です。これらの演奏者の全容を見ることができるところにこのDVDの大きな価値があります。
オラトリオのような壮大な曲ですが,1910年9月にドイツ・ミュンヘンで初演されたこの曲は,1975年年のザルツブルグでの演奏が,作曲以来,オーストリア国内での2度目の演奏だったようです。
この大曲が母国オーストリアであまり演奏されてこなかった理由は,この曲の作風というよりも,演奏を行うための費用にあったようです。
レナード・バーンスタイン指揮のマーラー作曲交響曲をDVDで聞いてまいりましたが,今日は第8番にしました。
この曲は,後に言われるようになった「千人の交響曲」のとおり,巨大な演奏者群を要する大作です。
フルオーケストラのほか,パイプオルガン,男声,女声ノソリスト8人,今回は3つの合唱団(それぞれに合唱指揮者)等,この演奏会を聞くことができる人は幸せと言えるでしょう。
今回の演奏は,1975年8月のザルツブルグ音楽祭にこの曲が演奏されたのを機会にウィーンで演奏されたライブDVDです。
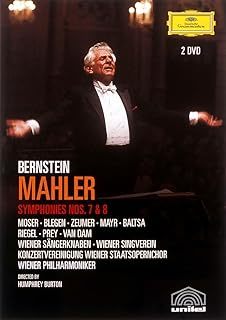
1975年8月,9月ウィーン,コンツェルトハウス レナード・バーンスタイン指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 5人の女声ソリスト,3人の男声ソリスト ウィーン国立歌劇場合唱団,ウィーン楽友協会合唱団,ウィーン少年合唱団
第1部と第2部に構成され,第1部はラテン語による聖歌,第2部はゲーテの「ファウスト」第2部の最後の部分をテキストにしているそうです。
この曲は,全曲,声楽と管弦楽,オルガンが一体となり奏でられる,いわば「合唱交響曲」です。
ベートーヴェン」の第9では第4楽章だけですし,マーラーの他の曲でも一部の楽章ですから,形の上でも一線を画している巨大な曲です。
第1部はパイプオルガンと合唱が聞く者を圧倒します。
第2部はソリスト,合唱がファウストからのテキストを歌い,オーケストラと最終章に至ります。
声楽ソリスト,合唱,オーケストラ渾身の演奏です。これらの演奏者の全容を見ることができるところにこのDVDの大きな価値があります。
オラトリオのような壮大な曲ですが,1910年9月にドイツ・ミュンヘンで初演されたこの曲は,1975年年のザルツブルグでの演奏が,作曲以来,オーストリア国内での2度目の演奏だったようです。
この大曲が母国オーストリアであまり演奏されてこなかった理由は,この曲の作風というよりも,演奏を行うための費用にあったようです。
バーンスタイン/マーラー交響曲第2番「復活」 [音楽]
関東の雪予報も収まったようですが,その間,青森市は大した降雪もなく土曜を迎えました。
それでも,気温は平年よりも低く寒い日が続いています。
ここ何回か,レナード・バーンスタイン指揮によるマーラーの交響曲をDVDで聞いて(見て)います。
今日は,バーンスタインの十八番ともいえる交響曲第2番「復活」です。
高校生の頃,バーンスタインの復活のLPを目にしていましたが,LP2枚の大作には手を出せず,名曲喫茶店で聞いていました。
年を取り,今は,バーンスタインがニューヨーク・フィルハーモニックを指揮したCBSのセット,晩年のグラモフォンのセットとその中間にある,グラモフォン(ユニテル)のDVDを保有していますが,今回改めてバーンスタイン50代の脂の乗り切った時代のライブのDVDを聞いて,マーラーに寄せる気迫を思い知りました。
今日の演奏は,1973年9月,イギリス・エジンバラ音楽祭におけるイーリー大聖堂でのライブ録音です。
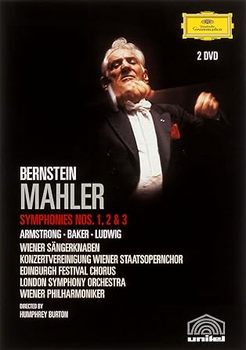
シーラ・アームストロング(ソプラノ),ジャネット・ベイカー(メゾソプラノ),エジンバラ音楽祭合唱団,合唱指揮:アーサー・オールダム,レナード・バーンスタイン指揮ロンドン交響楽団
全5楽章,約1時間半にわたる大作です。
マーラーは交響曲第2番,第3番,第4番はソプラノ,メゾソプラノのソロ,あるいは合唱などとオーケストラが演奏する形をとっており,2番,3番,4番の3つの交響曲を角笛3部作と言われています。
私など無宗教の人間には,「復活」と言ってもすぐには理解できませんが,この曲の後半,ソリスト,合唱によって「滅びるものは常によみがえる。生きるための用意をせよ。」「よみがえるために私は死ぬのだ!私はよみがえるだろう!」と歌われます。
声楽が素晴らしい。ソプラノ,メゾソプラノ,合唱が一体となり,石造の大聖堂に鳴り響きます。
圧倒的な金管群と2台のハープが印象的です。ホルン群は大聖堂の上方に向けてうやうやしく捧げるように吹き上げます。
バーンスタインの全身全霊の指揮,合唱団に向け自ら口ずさみながら,笑顔を投げかけながらの指揮です。
私は,昨日の午後,今朝早朝の2回このDVDを見ましたが,曲の終了時には体が震えるようでした。
ライブの動画は素晴らしいです。
DVDの解説には,バーンスタインにとって,2番「復活」は今や名刺代わりのようなものだと書いてありますが,私にとっても,バーンスタインは,復活が常に頭にあるでしょう。
それでも,気温は平年よりも低く寒い日が続いています。
ここ何回か,レナード・バーンスタイン指揮によるマーラーの交響曲をDVDで聞いて(見て)います。
今日は,バーンスタインの十八番ともいえる交響曲第2番「復活」です。
高校生の頃,バーンスタインの復活のLPを目にしていましたが,LP2枚の大作には手を出せず,名曲喫茶店で聞いていました。
年を取り,今は,バーンスタインがニューヨーク・フィルハーモニックを指揮したCBSのセット,晩年のグラモフォンのセットとその中間にある,グラモフォン(ユニテル)のDVDを保有していますが,今回改めてバーンスタイン50代の脂の乗り切った時代のライブのDVDを聞いて,マーラーに寄せる気迫を思い知りました。
今日の演奏は,1973年9月,イギリス・エジンバラ音楽祭におけるイーリー大聖堂でのライブ録音です。
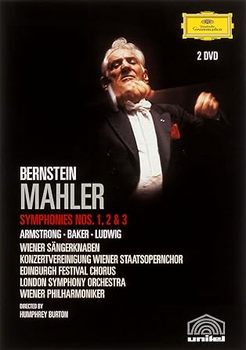
シーラ・アームストロング(ソプラノ),ジャネット・ベイカー(メゾソプラノ),エジンバラ音楽祭合唱団,合唱指揮:アーサー・オールダム,レナード・バーンスタイン指揮ロンドン交響楽団
全5楽章,約1時間半にわたる大作です。
マーラーは交響曲第2番,第3番,第4番はソプラノ,メゾソプラノのソロ,あるいは合唱などとオーケストラが演奏する形をとっており,2番,3番,4番の3つの交響曲を角笛3部作と言われています。
私など無宗教の人間には,「復活」と言ってもすぐには理解できませんが,この曲の後半,ソリスト,合唱によって「滅びるものは常によみがえる。生きるための用意をせよ。」「よみがえるために私は死ぬのだ!私はよみがえるだろう!」と歌われます。
声楽が素晴らしい。ソプラノ,メゾソプラノ,合唱が一体となり,石造の大聖堂に鳴り響きます。
圧倒的な金管群と2台のハープが印象的です。ホルン群は大聖堂の上方に向けてうやうやしく捧げるように吹き上げます。
バーンスタインの全身全霊の指揮,合唱団に向け自ら口ずさみながら,笑顔を投げかけながらの指揮です。
私は,昨日の午後,今朝早朝の2回このDVDを見ましたが,曲の終了時には体が震えるようでした。
ライブの動画は素晴らしいです。
DVDの解説には,バーンスタインにとって,2番「復活」は今や名刺代わりのようなものだと書いてありますが,私にとっても,バーンスタインは,復活が常に頭にあるでしょう。
バーンスタイン/マーラー交響曲第1番「巨人」 [音楽]
青森市は朝少し雪が降り,その後は曇り空です。関東は雪の心配があるとか?春が近いのに一気に暖かくなりませんね。
来週は気温が上昇するとか。自宅前の木蓮,桜,梅などの蕾も膨らむでしょう。
1か月もすると,青森でも桜の開花でニュースが盛り上がるでしょう。
今日は,午前中に仕事を片付け,相変わらずマイオーディオで音楽三昧です。
今日は,バーンスタイン指揮でマーラーの交響曲第1番「巨人」です。
昔,高校のころですから,50数年前,レコード店では,ブルーノ・ワルター指揮の「巨人」とバーンスタイン指揮の「復活」のポスターが目につきました。
マーラーの曲では,この交響曲から始まりましたから,これまで一番聞いたのはこの曲かもしれません。
マーラー作曲交響曲第1番「巨人」をレナード・バーンスタインの指揮のDVDを聞く(見る)ことにしました。
私の手許には,バーンスタインのマーラーの交響曲全集として,CBSのニューヨーク・フィルハーモニックのCDセット,今回のDVD,そして最後のCDセット(グラモフォン)の計3セットがありますが,すべて丹念に聞き終えたわけではありません。
仕事を終えて後,好きなこと,やり残したことをするつもりですが,数あるLP,CD,DVDなどを聞きなおすのもこれからの楽しみの一つです。
今回は,バーンスタイン50代のコンサート・ライブのDVDを聞いていますが今日はその3回目,第1番「巨人」です。
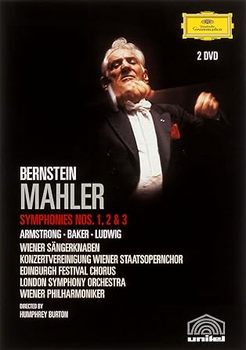 1974年10月,ウィーン コンツェルトハウス(ライブ) ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
1974年10月,ウィーン コンツェルトハウス(ライブ) ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
1番「巨人」は,マーラー最初の交響曲です。
第1楽章の出だしは,緩やかで,まるでベートーヴェンの第6番「田園」のようです。クラリネットのカッコウの声のようなメロディーに導かれるように始まり,第5楽章の嵐のようなクライマックスが待っています。
後期ロマン派の色濃い曲ですが,最後の10番(未完成)まで,マーラーは苦悩に満ちた曲を作り続けます。
次は,第2番「復活」にします。
来週は気温が上昇するとか。自宅前の木蓮,桜,梅などの蕾も膨らむでしょう。
1か月もすると,青森でも桜の開花でニュースが盛り上がるでしょう。
今日は,午前中に仕事を片付け,相変わらずマイオーディオで音楽三昧です。
今日は,バーンスタイン指揮でマーラーの交響曲第1番「巨人」です。
昔,高校のころですから,50数年前,レコード店では,ブルーノ・ワルター指揮の「巨人」とバーンスタイン指揮の「復活」のポスターが目につきました。
マーラーの曲では,この交響曲から始まりましたから,これまで一番聞いたのはこの曲かもしれません。
マーラー作曲交響曲第1番「巨人」をレナード・バーンスタインの指揮のDVDを聞く(見る)ことにしました。
私の手許には,バーンスタインのマーラーの交響曲全集として,CBSのニューヨーク・フィルハーモニックのCDセット,今回のDVD,そして最後のCDセット(グラモフォン)の計3セットがありますが,すべて丹念に聞き終えたわけではありません。
仕事を終えて後,好きなこと,やり残したことをするつもりですが,数あるLP,CD,DVDなどを聞きなおすのもこれからの楽しみの一つです。
今回は,バーンスタイン50代のコンサート・ライブのDVDを聞いていますが今日はその3回目,第1番「巨人」です。
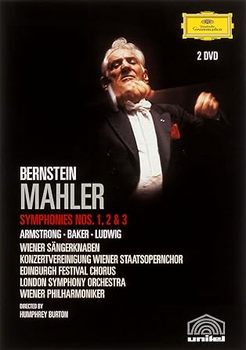 1974年10月,ウィーン コンツェルトハウス(ライブ) ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
1974年10月,ウィーン コンツェルトハウス(ライブ) ウィーンフィルハーモニー管弦楽団1番「巨人」は,マーラー最初の交響曲です。
第1楽章の出だしは,緩やかで,まるでベートーヴェンの第6番「田園」のようです。クラリネットのカッコウの声のようなメロディーに導かれるように始まり,第5楽章の嵐のようなクライマックスが待っています。
後期ロマン派の色濃い曲ですが,最後の10番(未完成)まで,マーラーは苦悩に満ちた曲を作り続けます。
次は,第2番「復活」にします。
バーンスタイン/マーラー交響曲第5番 [音楽]
暖冬少雪と言われる今冬も,もう啓蟄,地中の虫もはい出てくる季節です。
我が家の鉢植えどころか,庭の福寿草の花芽が膨らんできました。
しかし,ここ2,3日降雪があり,日中でも最高気温4,5℃,寒い毎日です。
1,2月は,暇な毎日でしたが,3月に入り,地中の虫のように慌ただしくなってきました。
午前中は相続登記やら,何やかやと走り回り,昼からバーンスタイン指揮のマーラーを見て(聞いて)います。
今日は,前回の4番に続きマーラー作曲交響曲第5番にしました。
5番と言えば,ルキノ・ヴィスコンティの監督作品「ヴェニスに死す」に使用された第4楽章(アダージェット)によって,マーラーの交響曲の中で最もポピュラーかもしれません。
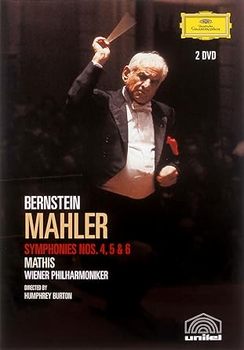 1972年4月,ウィーンフィルハーモニー管弦楽団,ウィーン・ムジークフェラインザール収録
1972年4月,ウィーンフィルハーモニー管弦楽団,ウィーン・ムジークフェラインザール収録
バースタイン50代の渾身の神がかり的演奏は,この曲のベストだと思っています。
アダージェットの指揮ぶりに聞く方も全身の力が引き寄せられます。
この曲のハイライトはアダージェットだけではありません。
是非,冒頭のトランペットのソロを聞いていただきたいのです。
この先を暗示しているようなトランペットです。
我が家の鉢植えどころか,庭の福寿草の花芽が膨らんできました。
しかし,ここ2,3日降雪があり,日中でも最高気温4,5℃,寒い毎日です。
1,2月は,暇な毎日でしたが,3月に入り,地中の虫のように慌ただしくなってきました。
午前中は相続登記やら,何やかやと走り回り,昼からバーンスタイン指揮のマーラーを見て(聞いて)います。
今日は,前回の4番に続きマーラー作曲交響曲第5番にしました。
5番と言えば,ルキノ・ヴィスコンティの監督作品「ヴェニスに死す」に使用された第4楽章(アダージェット)によって,マーラーの交響曲の中で最もポピュラーかもしれません。
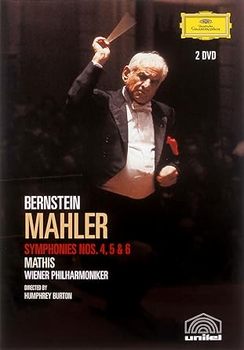 1972年4月,ウィーンフィルハーモニー管弦楽団,ウィーン・ムジークフェラインザール収録
1972年4月,ウィーンフィルハーモニー管弦楽団,ウィーン・ムジークフェラインザール収録バースタイン50代の渾身の神がかり的演奏は,この曲のベストだと思っています。
アダージェットの指揮ぶりに聞く方も全身の力が引き寄せられます。
この曲のハイライトはアダージェットだけではありません。
是非,冒頭のトランペットのソロを聞いていただきたいのです。
この先を暗示しているようなトランペットです。
バーンスタイン/マーラー交響曲第4番 [音楽]
昨日,今日と大雪注意報が出ていました。
昨日の降雪は10㎝足らず,今朝は15㎝くらいで,交通に支障はないでしょう。
まだ野外活動をするには至らず,寒い日曜日は,音楽ソースの活用です。
レナード・バーンスタインのDVDを見る(聞く)ことにしました。
最近,LPやCDを聞くよりは,ライブの音楽音源を視聴することが多くなっています。
セッション録音の方が音質はいいでしょうが,臨場感に欠けます。そして何よりも聴衆の反応を見ることができるからです。YouTubeという方法もありますが,できればマイ・オーディオを活用したいので,DVDやブルーレイでということになります。
前置きが長くなりましたが,私は,レナード・バーンスタインを敬愛しています。
作曲家,ピアニスト,指揮者,教育者など音楽家として,バッハの時代の音楽家のように音楽世界に功績を残した大音楽家です。
彼の残した膨大な音楽遺産の中から,マーラーの交響曲全曲をDVDによって聞いてみたいと思います。
言うまでもなく,クラシック音楽界でバーンスタインがマーラー・ブームを巻き起こしたと言われています。
今日は,手始めにマーラーの交響曲第4番にしました。
この曲は,マーラーの作品の中で,1時間を超える大作でもなく,まるでメルヘンの世界にいるような楽しい曲です。
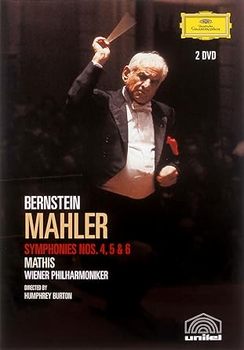
1972年5月,ウィーン,ムジークフェラインザール,ウィーンフィルハーモニー管弦楽団ライブ
ソプラノ:エディット・マティス
第1楽章の馬車の鈴の音のような出だしからメルヘンの世界にいざなわれます。
第4楽章のソプラノ(子供の不思議な角笛)が,オーケストラと一体となり,マーラーの音楽世界を表現します。
50代半ばのバーンスタインの精力的でダイナミックな指揮ぶりに圧倒されます。
ライブのDVDでなければ体験できません。
バーンスタインのマーラー交響曲全曲のDVDを保有していますから,徐々に感想をupしたいと思っています。
昨日の降雪は10㎝足らず,今朝は15㎝くらいで,交通に支障はないでしょう。
まだ野外活動をするには至らず,寒い日曜日は,音楽ソースの活用です。
レナード・バーンスタインのDVDを見る(聞く)ことにしました。
最近,LPやCDを聞くよりは,ライブの音楽音源を視聴することが多くなっています。
セッション録音の方が音質はいいでしょうが,臨場感に欠けます。そして何よりも聴衆の反応を見ることができるからです。YouTubeという方法もありますが,できればマイ・オーディオを活用したいので,DVDやブルーレイでということになります。
前置きが長くなりましたが,私は,レナード・バーンスタインを敬愛しています。
作曲家,ピアニスト,指揮者,教育者など音楽家として,バッハの時代の音楽家のように音楽世界に功績を残した大音楽家です。
彼の残した膨大な音楽遺産の中から,マーラーの交響曲全曲をDVDによって聞いてみたいと思います。
言うまでもなく,クラシック音楽界でバーンスタインがマーラー・ブームを巻き起こしたと言われています。
今日は,手始めにマーラーの交響曲第4番にしました。
この曲は,マーラーの作品の中で,1時間を超える大作でもなく,まるでメルヘンの世界にいるような楽しい曲です。
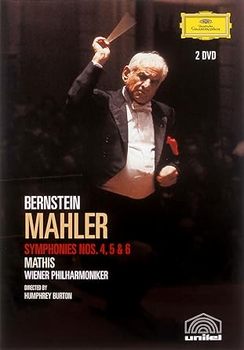
1972年5月,ウィーン,ムジークフェラインザール,ウィーンフィルハーモニー管弦楽団ライブ
ソプラノ:エディット・マティス
第1楽章の馬車の鈴の音のような出だしからメルヘンの世界にいざなわれます。
第4楽章のソプラノ(子供の不思議な角笛)が,オーケストラと一体となり,マーラーの音楽世界を表現します。
50代半ばのバーンスタインの精力的でダイナミックな指揮ぶりに圧倒されます。
ライブのDVDでなければ体験できません。
バーンスタインのマーラー交響曲全曲のDVDを保有していますから,徐々に感想をupしたいと思っています。
ホロヴィッツ・アット・ホーム [音楽]
昨日は立春,寒も明け,暦の上ではいよいよ春です。
野外活動が待ち遠しい。
じっと屋内に籠り,しばらくウラジミール・ホロヴィッツの晩年のCDを聞いてきましたが,今日は,ホロヴィッツの最後に,彼がニューヨーク・マンハッタンの自宅で録音した「ホロヴィッツ・アット・ホーム」を聞きます。
ホロヴィッツの最初に紹介した,1965年の「ヒストリック・リターン・コンサート」のボーナスDVD
に自宅でピアノを弾くホロヴィッツの様子が収録されています。
部屋のソファーには夫人のワンダ・トスカニーニ・ホロヴィッツが腰掛け,ホロヴィッツの話に耳を傾けています。そう,その名のとおり,夫人はトスカニーニのお嬢さんなのです。
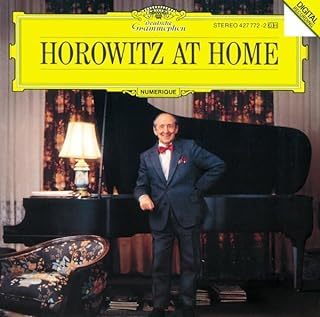
あのような部屋で録音したのが今回の「ホロヴィッツ・アット・ホーム」なのです。
1986年2月,1988年12月,1989年1月に,ホロヴィッツの体調の良い時期と気の向いたときに録音されたものと思われます。
モーツァルトのソナタK281,シューベルトの楽興の時,シューベルト/リストのセレナードなど気楽にしかも心穏やかになる曲ばかりです。
私は,軽やかで心浮き浮きするモーツァルト,そして,シューベルトのこの2曲にも感動しました。
何しろピアノの音が明るく鮮明で,ホロヴィッツの表情が目に見えるようです。
ホロヴィッツは,1989年11月5日,自宅で食事中に亡くなりました。
ホロヴィッツは,ミラノのトスカニーニの墓苑に寄り添うように埋葬されているそうです。
野外活動が待ち遠しい。
じっと屋内に籠り,しばらくウラジミール・ホロヴィッツの晩年のCDを聞いてきましたが,今日は,ホロヴィッツの最後に,彼がニューヨーク・マンハッタンの自宅で録音した「ホロヴィッツ・アット・ホーム」を聞きます。
ホロヴィッツの最初に紹介した,1965年の「ヒストリック・リターン・コンサート」のボーナスDVD
に自宅でピアノを弾くホロヴィッツの様子が収録されています。
部屋のソファーには夫人のワンダ・トスカニーニ・ホロヴィッツが腰掛け,ホロヴィッツの話に耳を傾けています。そう,その名のとおり,夫人はトスカニーニのお嬢さんなのです。
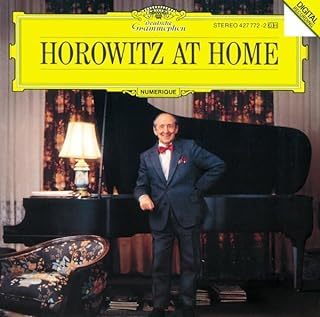
あのような部屋で録音したのが今回の「ホロヴィッツ・アット・ホーム」なのです。
1986年2月,1988年12月,1989年1月に,ホロヴィッツの体調の良い時期と気の向いたときに録音されたものと思われます。
モーツァルトのソナタK281,シューベルトの楽興の時,シューベルト/リストのセレナードなど気楽にしかも心穏やかになる曲ばかりです。
私は,軽やかで心浮き浮きするモーツァルト,そして,シューベルトのこの2曲にも感動しました。
何しろピアノの音が明るく鮮明で,ホロヴィッツの表情が目に見えるようです。
ホロヴィッツは,1989年11月5日,自宅で食事中に亡くなりました。
ホロヴィッツは,ミラノのトスカニーニの墓苑に寄り添うように埋葬されているそうです。
ホロヴィッツ・プレイズ・モーツァルト [音楽]
今日は節分,明日は立春ですが,冬型の気圧配置がやや緩みつつあるようです。
今朝,10㎝未満の除雪をしましたが,今冬は今のところ暖冬少雪です。
60代からのウラジミール・ホロヴィッツを聞き続けてきましたが,今日は,最晩年,イタリア出身のレジェンド,カルロ・マリア・ジュリーニを指揮者にむかえたモーツァルトのピアノ協奏曲第23番とピアノソナタK333にしました。
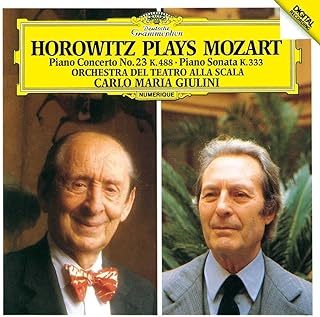
1987年3月,カルロ・マリア・ジュリーニ指揮ミラノスカラ座管弦楽団,ミラノ,アバネラ・スタジオの録音。グラミー賞を受賞しています。
この録音風景は,NHKの夜のクラシック番組でも放映され,当時84歳のホロヴィッツとハンサムなジュリーニの打ち合わせの情景が映し出されました。
その時以来,モーツァルトの協奏曲23番が大好きになりました。
ブゾーニのカデンツァによる長い第1楽章,憂いを帯びた第2楽章,少し早めの快活な第3楽章,楽しい演奏です。
加えて,ピアノソナタK.333,転がるようなピアノの音が美しい。ジャケットのホロヴィッツの顔からもうかがえるような温かく楽しいピアノソナタです。
数回にわたってホロヴィッツ晩年の録音を聞いてきましたが,もう1回ホロヴィッツを聞くことにします。
明日は立春です。春はまだ遠いか
今朝,10㎝未満の除雪をしましたが,今冬は今のところ暖冬少雪です。
60代からのウラジミール・ホロヴィッツを聞き続けてきましたが,今日は,最晩年,イタリア出身のレジェンド,カルロ・マリア・ジュリーニを指揮者にむかえたモーツァルトのピアノ協奏曲第23番とピアノソナタK333にしました。
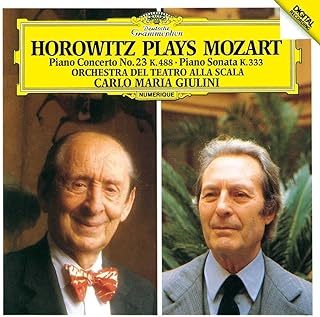
1987年3月,カルロ・マリア・ジュリーニ指揮ミラノスカラ座管弦楽団,ミラノ,アバネラ・スタジオの録音。グラミー賞を受賞しています。
この録音風景は,NHKの夜のクラシック番組でも放映され,当時84歳のホロヴィッツとハンサムなジュリーニの打ち合わせの情景が映し出されました。
その時以来,モーツァルトの協奏曲23番が大好きになりました。
ブゾーニのカデンツァによる長い第1楽章,憂いを帯びた第2楽章,少し早めの快活な第3楽章,楽しい演奏です。
加えて,ピアノソナタK.333,転がるようなピアノの音が美しい。ジャケットのホロヴィッツの顔からもうかがえるような温かく楽しいピアノソナタです。
数回にわたってホロヴィッツ晩年の録音を聞いてきましたが,もう1回ホロヴィッツを聞くことにします。
明日は立春です。春はまだ遠いか
ホロヴィッツ・イン・モスクワ [音楽]
寒波来襲の2月1日です。2日ほど寒い日が続くようです。
今日は年1度の市の健康診断(半日ドックのようなもの)で,朝一からかかりつけ医で見てもらいました。結果は後日,果たして?
仕事2件を片付けて,ホロヴィッツを聞いています。
今日の1枚は「ホロヴィッツ・イン・モスクワ」,1986年モスクワ音楽院大ホールのライブ録音です。
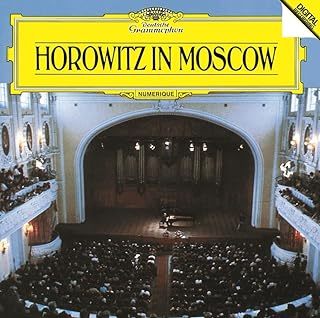
20代のホロヴィッツが,祖国を離れて60年ぶりに故国の聴衆の前で演奏したものです。
自国出身の大演奏家を,今や円熟の老演奏家としてモスクワの聴衆は最初から最後まで大歓声と拍手で迎えます。
日本では,しわくちゃの老批評家からひどい表現の感想を言われましたが,それを気にしたホロヴィッツは,体調を整え再度訪日したのでした。
スカルラッティ,モーツァルトのソナタ,ラフマニノフの前奏曲,スクリャービンの練習曲,シューベルト/リストのウィーンの夜会,リストの巡礼の年第2年<イタリア>から,ショパンのマズルカ2曲,トロイメライ,モシュコフスキーの花火,ラフマニノフのW.Rのポルカ,これが演奏曲ですが,ラフマニノフ,スクリャービン,リストが特にいいですね。
さすがに故国らしく,ラフマニノフの曲を弾いた演奏者にも作曲者にも拍手喝采は鳴りやみません。
故国訪問の3年後にホロヴィッツは亡くなります。
今日は年1度の市の健康診断(半日ドックのようなもの)で,朝一からかかりつけ医で見てもらいました。結果は後日,果たして?
仕事2件を片付けて,ホロヴィッツを聞いています。
今日の1枚は「ホロヴィッツ・イン・モスクワ」,1986年モスクワ音楽院大ホールのライブ録音です。
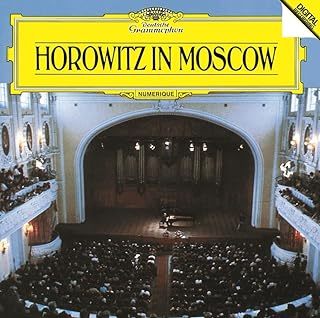
20代のホロヴィッツが,祖国を離れて60年ぶりに故国の聴衆の前で演奏したものです。
自国出身の大演奏家を,今や円熟の老演奏家としてモスクワの聴衆は最初から最後まで大歓声と拍手で迎えます。
日本では,しわくちゃの老批評家からひどい表現の感想を言われましたが,それを気にしたホロヴィッツは,体調を整え再度訪日したのでした。
スカルラッティ,モーツァルトのソナタ,ラフマニノフの前奏曲,スクリャービンの練習曲,シューベルト/リストのウィーンの夜会,リストの巡礼の年第2年<イタリア>から,ショパンのマズルカ2曲,トロイメライ,モシュコフスキーの花火,ラフマニノフのW.Rのポルカ,これが演奏曲ですが,ラフマニノフ,スクリャービン,リストが特にいいですね。
さすがに故国らしく,ラフマニノフの曲を弾いた演奏者にも作曲者にも拍手喝采は鳴りやみません。
故国訪問の3年後にホロヴィッツは亡くなります。



